「片づけをルーティンにしたいけれど、三日坊主で終わってしまう…」
片づけが続かないのは、意志ややる気の問題ではありません。
人は毎日数万回の判断をしているため、「片づけをするかどうか」を考え続けること自体が大きな負担になるのです。
今回は
- 自然と続く片づけルーティンの作り方
- 生活の流れに合わせたルーティン化のコツ
- やってしまいがちな失敗例
を解説します。
ぜひ、参考にしてくださいね。
片づけはルーティンを作るとラクに続く
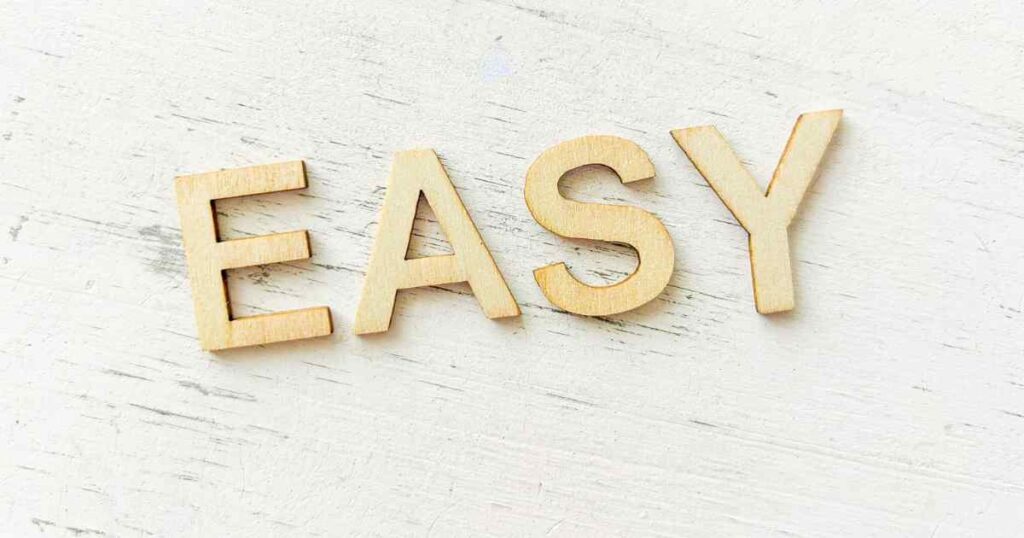
片づけは「やる気」や「根性」だけに頼ると、長続きしません。
大切なのは、毎日の暮らしの中に自然と組み込めるルーティンをつくることです。
片づけルーティンがあると、散らかってもリセットがしやすくなり、無理なく整った部屋を保てます。
片づけルーティンを身につけるうえで、押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。
片づけが続かないのは意志の問題じゃない
片づけは1度やって終わりではありません。
生活している以上、定期的に必要になります。
しかし、意志の力だけに頼ると三日坊主になりやすいのも事実です。
片づけが続かない理由は、「やる気」や「根性」の有無だけではありません。
調査によると、成人は一日に約33,000~35,000回もの判断や選択を行っていると報告されています。
(参考:ハーバードビジネスレビュー)
これほど膨大な判断をしていれば、「片づけをするかどうか」の選択すら脳にとって大きな負担になります。
だからこそ、整った部屋を保つためには、ルーティンのような仕組みづくりが欠かせません。
モノに定位置がないと散らかる
ルーティンを作る前に、押さえておきたいことがあります。
1つは、モノの住所を決めることです。
住所が決まっていないモノは、使ったあとに元へ戻しにくくなります。
戻す場所に迷うと脳に負担がかかり、
「めんどうだから、とりあえず置いておこう」
と適当に置いてしまいがちです。
その結果、部屋は再び散らかり、負のループに陥ります。
お財布やスマホが、ダイニングやキッチン、バッグの中に点在している人は要注意です。
モノに住所をつけることで、片づけルーティンをスムーズに作れるようになります。
自然に片づくルーティンの作り方

片づけルーティンは、難しいことを一気にやる必要はありません。
ちょっとした工夫を取り入れるだけで、無理なく自然に片づけられる仕組みがつくれます。
すぐに取り入れられる「自然に片づくルーティンの作り方」を3つのステップでご紹介します。
1つだけ定位置を決める
最初は1つだけ、モノの定位置を決めましょう。
すべてのモノに定位置をつくるのが理想ですが、最初から大きく取り組むと挫折しやすくなります。
まず1つだけ定位置を設定してみてください。
- 玄関にカギ置きトレイを用意する
- バッグはクローゼットの中にしまう
定位置が1つ決まるだけで、迷わないラクさを実感できます。
使う場所にモノをしまう
定位置の便利さを体感したら、少しずつ他のモノの定位置も決めていきましょう。
定位置を決める基本は、使う場所の近くに設定することです。
- ティッシュはリビングに置く
- カッターはダンボールを開く機会が多い玄関にしまう
このように、普段よく使う場所を思い浮かべながら定位置を決めると、モノが自然と片づきます。
ルーティンはタイミングで組み込む
定位置を決めたら、次は片づけのルーティンを考えましょう。
ルーティンづくりの基本は、時間よりも「タイミング」をきっかけにすることです。
「毎日20時に15分片づけをする」
ではなく
「毎日夕飯後に15分片づけをする」
このように、日常の行動の流れに組み込むと忘れにくくなります。
続けることで身体が自然と動き、意志の力に頼らず行動できるようになります。
目につく場所からルーティン化する
片づけのルーティンも、一気に習慣づけようとすると挫折しやすくなります。
おすすめは、目につく場所の片づけをルーティン化することです。
変化が目に入ると気持ちよさを感じ、習慣化につながります。
- 洗面台
- ダイニングテーブル
- キッチンカウンター
このような場所が取り組みやすいでしょう。
小さな達成感と快適さが、次の行動を自然に引き出してくれます。
片づけのルーティンを作りたい人にありがちな落とし穴3選

片づけルーティンを作ろうとしても、気づかないうちに誤った方法を選んでしまう人は少なくありません。
勢いではじめても続かず、かえって片づけがストレスになる場合もあります。
ここでは、片づけルーティンをつくるときに多くの人が陥りやすい3つの落とし穴を紹介します。
気合いと根性に頼る
ルーティンが崩れると、つい
- 今日は一気に片づけるぞ!
- キッチンを1日で完璧にキレイにする!
などと考えてしまいます。
気合と根性の片づけは要注意です。
繰り返すと
「片づけは疲れるからやりたくない」
というネガティブな感情が植え付けられてしまいます。
ルーティンが一度崩れても、今日から少しずつ再開すれば大丈夫です。
無理しすぎないことが、片づけを長く続ける一番の方法です。
「完璧な収納」を目指しすぎてしまう
定位置を決めるとき、インスタで見かけるような完璧な収納を目指したくなります。
しかし、見た目の美しさと自宅での使いやすさは、必ずしも一致しないため注意が必要です。
- 色別や長さ別にきれいに並べても、数週間後には乱れてしまう
- オープン棚にきれいに並べても、ほこりが気になり掃除の手間が増える
SNSの収納は参考程度にとどめ、自宅の暮らしに合った方法を選びましょう。
収納グッズを勢いで買ってしまう
定位置を決めるときにありがちなのが、深く考えずに収納グッズを買ってしまうことです。
先に買ってしまうと、サイズが合わなかったり、結局使わなくなることも多いです。
たとえば、一時的にモノを入れるつもりでバスケットを買ったものの、置き場がなく邪魔になってしまうケースはよくあります。
収納グッズを買う前に、まずはモノを減らせないか見直しましょう。
そのうえで、「どのモノを、どの収納に入れるか」を具体的に計画すると失敗しにくくなります。
片づけのルーティンがあれば「きれい」は続く
片づけは一生続く行動です。
だからこそ、頑張らなくても整った部屋を保てるルーティン作りが大切になります。
コツを押さえて、片づけのルーティンづくりにぜひ挑戦してみてください。
それでも片づけがうまくいかない人、収納場所をプロに相談したい人は、整理収納学園に参加してみませんか。
整理収納学園では、仲間と片づけの報告を共有したり、活躍している整理収納アドバイザーに直接相談できたりします。
新しい一歩を踏み出す場で、あなたの参加を心よりお待ちしています。


