「部屋を片づけないといけないのに、やる気が出ない。」
「片づけと脳の前頭葉の関連について知りたい。」
散らかった部屋を見るたびに自己嫌悪…なんて経験はありませんか?
実は、あなたの意志が弱いからではなく、脳の司令塔である「前頭葉(ぜんとうよう)」の働きが関係しているのかもしれません。
今回は
- 片づけと前頭葉の意外な関係性
- 脳を味方につけて、無理なく片づけを進めるコツ
などをご紹介します。
ぜひ参考にしてくださいね。
片づけができないのは脳の前頭葉が原因かもしれません

片づけられない自分を、意志が弱いせいだと責めていませんか。
片づけと前頭葉のつながりを理解するために、大切な3つのポイントをご紹介します。
- 片づけには「前頭葉の実行機能」が欠かせない
- 前頭葉が弱ると「やりたいのに動けない」という現象が起きる
- 前頭葉はストレスや疲労でもパフォーマンスが下がる
ひとつずつ、見ていきましょう。
片づけには「前頭葉の実行機能」が欠かせない
片づけは、ただモノを動かすだけの単純作業ではありません。
- どこから始めるか
- これは必要か不要か
- どこに収納するか
など、一連の作業には計画を立て、判断し、行動をコントロールする力が求められます。
この複雑なプロセスを担っているのが、前頭葉の「実行機能」と呼ばれる働きです。
目の前に散らかった部屋を前に
「どこから手をつけていいか分からない…」
とフリーズしてしまうことはありませんか?
これは、処理すべき情報が多すぎて、前頭葉が混乱し、計画を立てる機能がうまく働いていないときに起こります。
片づけが苦手なのは、決して性格ややる気だけの問題ではないのです。
前頭葉が弱ると「やりたいのに動けない」という現象が起きる
「片づけを始めなきゃ!」と頭では強く思っているのに、なぜか、ソファから立ち上がれない…。
こんな時は、思考を司る前頭葉から、体の動きを指令する運動野への信号がスムーズに連携できていないときに起こります。
片づけをしようと思ったはずが、気づけば何時間もスマホを眺めていた…というのも典型的な例です。
必要以上に自分を責めず、脳の仕組みによる反応だと知っておきましょう。
前頭葉はストレスや疲労でもパフォーマンスが下がる
前頭葉は、脳の中でも特に繊細で、ストレスや疲労の影響を受けやすい部分です。
強いストレスを感じると「コルチゾール」というホルモンが分泌され、前頭葉の働きを鈍らせ、判断力や集中力を低下させることが分かっています。
毎日の育児や家事に追われ、心も体もクタクタ…。
そんなときは、脳もエネルギー切れを起こしています。
「なんだか今日はやる気が出ないな」と感じたら、脳が休息を求めているのかもしれません。
「今日は休む日」と割り切ることも大切です。
片づけは前頭葉の働きでスムーズにいくか決まる

前頭葉の働きが鈍ると、片づけの際にさまざまな困りごとが起こります。
片づけたい気持ちはあるのに、なぜかうまくいかないなら、前頭葉の機能低下が原因かもしれません。
前頭葉がうまく働かない場合に起こりがちな状況を、3つご紹介します。
- 片づけが「先延ばし」になるのは前頭葉の混乱
- 「視覚情報の多さ」が脳の処理を妨げる
- ADHDとの違い
具体的に見ていきましょう。
片づけが「先延ばし」になるのは前頭葉の混乱
前頭葉は、非常にエネルギー消費が激しく、疲れやすいという特徴があります。
そのため、少しでも複雑で面倒だと感じるタスクは、「後でやろう」と判断しがちになります。
「子どもが寝たらやろう」
「このテレビ番組が終わったらやろう」
と思っているうちに何もできずに一日が終わってしまった…というときは、前頭葉のエネルギー不足です。
「テーブルの上だけ拭く」など、無理のない範囲で“少しだけやることを意識するのが、先延ばしを防ぐコツです。
「視覚情報の多さ」が脳の処理を妨げる
モノであふれた部屋は、膨大な「視覚情報」の塊です。
私たちの脳は、意識していなくても目に入るモノをすべて情報として処理しようとするため、散らかった空間にいるだけで前頭葉は疲弊します。
まずは
- リビングのテーブルの上だけ
- キッチンのシンクの中だけ
というように「見える部分」を限定して片づけるのがおすすめです。
視覚情報が減るだけで、前頭葉の負担は軽くなり、次の行動に移りやすくなります。
ADHDでは?と不安になったら
片づけが極端に苦手だったり、集中力が続かなかったりすると、
「もしかして自分はADHD(注意欠如・多動症)なのでは?」
と不安に思う人もいるかもしれません。
ADHDの特性の一つに「実行機能の困難」があり、前頭葉の機能低下の症状とよく似ています。
片づけを始めてもすぐに他のことに気を取られたり、買い物の際に必要なモノを買い忘れたり…。
ADHDに見られる特性は、ストレスや疲労によって前頭葉の働きが落ちているときにも現れます。
もちろん、専門的な診断が必要な場合もあります。
しかし、大切なのは診断名よりも
「今の自分がラクに動くための工夫」
を見つけることです。
片づけられるようになりたい!前頭葉を味方につける3つのコツ
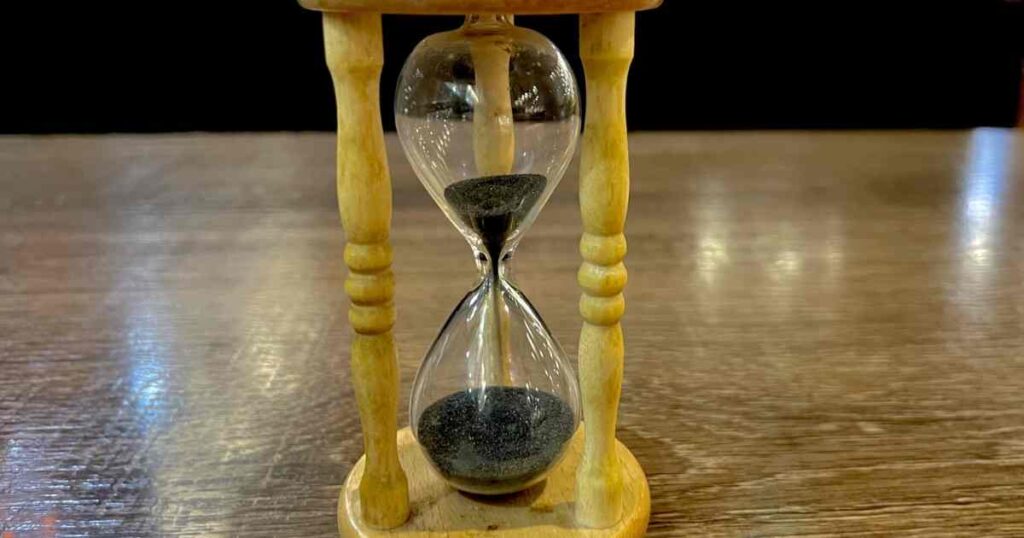
脳の仕組みが分かったら、前頭葉を「やる気モード」に切り替えるコツを試してみましょう。
誰でも簡単にできる3つの方法をご紹介します。
- タスクを細かくする
- ごほうびスイッチを入れる
- 未来を想像する
くわしく解説します。
タスクは1分で終わるレベルまで分解する
片づけにおいて最もエネルギーを使うのは、行動を開始する瞬間です。
最初のハードルを越えるために、タスクを極限まで小さく分解しましょう。
例えば「玄関を片づける」では、脳はまだ抵抗を感じます。
- 靴を一足だけ揃える
- DMをゴミ箱に捨てる
というように、1分以内で確実に終わるレベルまで分解してみましょう。
小さなタスクでも「できた!」という成功体験は、脳にとって最高の栄養です。
繰り返すことで、自己肯定感が高まり、前頭葉も鍛えられ、次の行動への意欲が湧いてきます。
「ごほうびスイッチ」で脳をその気にさせる
私たちの脳は、「これをやったら良いことがある」と分かると、やる気ホルモンである「ドーパミン」を分泌します。
この性質を利用して、自分自身にごほうびを用意しましょう。
- タイマーを10分セットして片づけたら、大好きなチョコを1つ食べる
- 引き出しを整理したら、雑誌をゆっくり読む
など、自分だけの「ごほうびルール」を作ってみましょう。
ポイントは、ごほうびを「楽しいこと」にすること。
ゲーム感覚で取り組むことで、脳は片づけは楽しいイベントだと錯覚し、スムーズに行動できるようになります。
未来を想像することで前頭葉が活性化する
前頭葉は、未来を想像したり、目標を立てたりするときに活発に働くという特性があります。
片づけに前頭葉の特性を活用するなら、インテリア雑誌やSNSでおしゃれな部屋の写真を探して
「こんなスッキリした部屋で、ハーブティーを飲んでくつろぎたいな」
などと具体的に想像しましょう。
想像することで前頭葉を刺激し、身体が動きやすくなります。
片づけで前頭葉をうまくに活かすために、意識したいこと
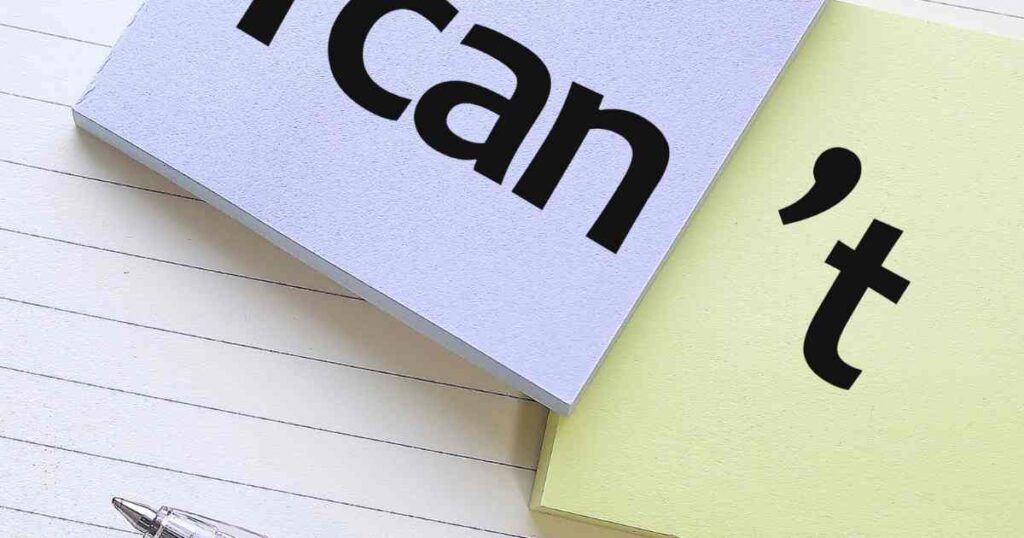
前頭葉の仕組みを理解すると、片づけへの向き合い方が楽になります。
心を軽くするために、特に大切にしたい3つのポイントをご紹介します。
- 「できない日」があっても当然と受け入れる
- 「片づけ=意志の強さ」ではないことを理解する
- 家族とのコミュニケーションも脳の視点を取り入れる
ひとつずつ、見ていきましょう。
「できない日」があっても当然と受け入れる
前頭葉のパフォーマンスには波があります。
体調や気分によって「どうしても動けない」日があるのは、自然なことです。
毎日完璧に片づいた状態をキープしようとすると、かえってストレスが溜まり、前頭葉を疲れさせてしまいます。
疲れているときは
「リビングの床に落ちているモノだけ拾う」
といったように、ハードルを下げましょう。
心に余裕を持つことで前頭葉のエネルギーを温存し、片づけを継続できるようになります。
「片づけ=意志の強さ」ではないことを理解する
片づけができるかどうかは、意志の強さではありません。
十分な睡眠がとれていなかったり、複数のタスクを同時にこなそうとしたりすると、誰でも前頭葉の機能は低下します。
前頭葉の機能が低下した状態で片づけができないのは、当たり前なのです。
脳が疲れていると感じたら、意識的に休息を取りましょう。
- 5分だけ目をつぶる
- 温かい飲み物を飲む
など、休む時間も、片づけのためには必要です。
家族とのコミュニケーションも脳の視点を取り入れる
家族から
「どうして片づけないの?」
「ちゃんと片づけて」
などと責められると、前頭葉は強いストレスを感じ、理性的な判断ができなります。
可能なら
「片づけられないのは、脳が疲れているから」
ということを家族に共有するのはいかがでしょうか。
自分だけでなく、家族も「片づけは脳のコンディションにも左右される」と知ることで、衝突が減るかもしれません。
お互いを理解し、思いやることが、快適な空間づくりの第一歩です。
片づけは前頭葉の働きが関係している
片づけと脳の前頭葉の関係性について解説しました。
片づけが進まない時は、脳の仕組みを理解し、上手に休憩を取り入れながら、1分でできることからはじめてみましょう。
それでも何からやっていいのかわからない、片づけのモチベーションを上げたい、という人は整理収納学園へ参加しませんか?
現役の整理収納アドバイザーに相談できたり、片づけを頑張る仲間たちと励まし合いながら整理を進められます。
ご入学をお待ちしています!


